地蔵堂をDIYで作ることになり、ブロックを積むところまで出来ました。
今回は積んだブロックの上に柱や梁といった基本構造を組んでいくところを紹介しようと思います。

材料
屋外で雨風に晒されるので本来なら腐食に強い材料が良いと思いますが、90×90ミリの米松を選びました。
これを選んだ理由は近所のホームセンターで安かったからです。
理想はウエスタンレッドシダーや防腐処理されたSPF材が良いと思います。
今回は外側の仕上げ材として焼き杉を使い、外側を覆うのでたぶん腐りにくいだろうと考えてこの材料を選びました。
それに腐ったらまた丈夫な材料で作り直せば良いと思います。
材料を切る
まずは土台を作りました。土台はブロックの上に配置する材料で、土台の上には柱を立てます。
手前側は地蔵をまつる為にスペースが必要なので、奥とサイドのみ土台を付けます。
まずは長さを測って切断しました。切断にはマキタの丸ノコ盤を使用しました。これは90ミリまできれいに切ることができ、以前のように数回に分けて切る必要が無くとても重宝しています。
もし45ミリぐらいの浅い丸ノコを使用する場合は是非この記事を参考にしてください。
長さを切る時は継手の分を計算に入れないと繋がらなくなってしまうので注意が必要です。土台部分は単純に辺の長さと同じにすれば大丈夫でしたが、僕は間違えて噛み合う分の長さ90ミリ短く切ってしまいました。
継手
今回は初めて木材の継ぎ手に挑戦しようと思いました。木造建築で釘を使わずに接合する日本の伝統技法で強度が出やすいらしいです。
かっこいいので前からやってみたいと思っていました。
継手にもいろんな種類があります。この土台部分で使ったのは相欠きとホゾ組みです。
個人的には手でのこぎりを使って切るイメージがあったのですが、丸ノコ盤を使いたかったので一度やってみました。
材料を立てて切るには不安定で危ないし、しかも正確に切れそうにないので材料を寝かせて何回も切れ込みを入れて作りました。
相欠きは半分ずつ切り欠いて嵌め合わせるだけで固定ができないのでビスを打っています。
ほぞ組みはほぞ穴(♀)を開け同じ大きさのほぞ(♂)を差し込みます。
ほぞ穴を作る時はドリルで大まかに開けて残ったところをノミで削りました。
ほぞ組みは差しているだけなので、方向によっては抜けてしまうので見えないところにビスをうっています。
強度を出す為に筋交いを入れるのが良いのですが、壁に板を貼る予定なので筋交いは無しにしました。
L字の金具が余っていたのでビスで打って補強しました。
次は屋根を作ります。

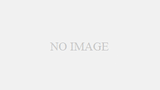
コメント